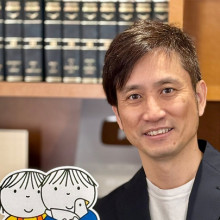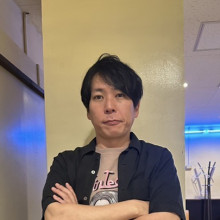安倍総理は、「コロナショックで民間の給与水準の先行きが心配されるなか、役所先行の定年延長が理解を得られるかどうかとの議論があるのは事実だ」とコロナ騒動に責任転嫁した。おそらく黒川弘務検事長の賭けマージャンが『週刊文春』にスクープされることを察知した官邸が、黒川検事長が辞任するのであれば、法案を強行する意味はないと判断したのだろう。
多くの評論家は、「検察官の定年延長の部分が問題だったのだから、一般の公務員の定年延長まで道連れで廃案にするのは、いかがなものか」と評した。私も、定年延長自体には反対しないが、問題は定年延長後の公務員の処遇だ。これまでの報道によると、公務員は60歳代前半に、それまでの給与の7割を受け取るようになるという。民間がそうなっているというのが、その根拠だ。
例えば、2019年の「賃金構造基本統計調査」によると、60歳代前半の平均年収は428万円と、50歳代前半よりも28%低くなっているから、3割減というのは妥当のようにみえる。
しかし、これは60歳代前半も、正社員として仕事を続けたときの比較だ。民間企業の場合、定年後は短時間勤務に変わることが多い。また、現在の公務員の60歳を過ぎてからの再任用の場合でも、およそ半数が短時間勤務になっている。そこで、60歳代前半の短時間勤務者の平均年収をみると、140万円となっている。つまり60歳の定年後に短時間勤務者になると、年収が76%も減るのだ。
さらに、定年を機に零細企業に移るケースも多い。これまでに示してきた数字は、企業規模10人以上のものだが、「賃金構造基本統計調査」は5〜9人規模の零細企業の賃金も調査している。そこで、10人以上規模の企業の正社員が60歳を機に、零細企業に移った場合を考えると、年収が597万円から389万円と35%減少することになるのだ。
実際、私の周囲でも、60歳の定年を機に再就職先を会社に面倒見てもらうと、年収が半分以下に落ちるというのが一般的だ。公務員でも、高級官僚が天下りするケースを除けば、同じような感じになっている。つまり、今回の国家公務員法の改正の本質は、60歳定年後に年収が半減していたものを3割減に抑える、つまり60歳代前半の年収を40%くらいアップさせるということなのだ。
私は、日本の公務員は一生懸命働いていると思う。しかし、あくまでも公務員の処遇は、民間の平均でなければならない。民間と比べて倒産やリストラのリスクがないのだから、民間の平均で十分だと思う。それを公務員だけ、60歳代前半に民間よりもはるかに高い処遇を受けるという仕組みは、許されるべきではないだろう。
国家公務員法と検察庁法などの10本の法律の「束ね法案」は、検察官の定年延長の部分に議論が集中して、本来の国家公務員の部分の議論がほとんどできていない。だから、国家公務員法の改正案が再び提出されたら、民間処遇とのバランスをきちんと議論すべきだ。日本を役人天国にしては、絶対にならないのだ。