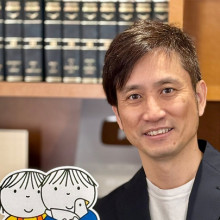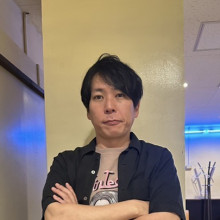同書では「モンペ」をいかにファッショナブルに着こなすかの大真面目な討論会や試作品が取り上げられている。これを今に置き換えれば、「いかにオシャレな布マスク」を手製するかに通じる現象だろう。
「大声では言えないが、次々と注文依頼がくるんですよ。今年は鯉のぼり需要がさっぱりだったから、これで少しは売り上げ回復です」
というのは幟旗などの問屋である。お気づきだろうか? 最近、身近な神社や寺院に「疫病退散」と白抜きされた幟が新たに掲揚されているのを。一種の「あやかり商法」と言ったら叱られそうではあるが、実は、この種の定番的方向性とはまったく異なる流行・拡散が起こっている。それが『妖怪アマビエ現象』。
この現象が今までと異なるのは、宗教(お祓いや、疫病退散の護摩焚き、祈願など)が発信源ではなく、宗教の方が後でSNSに乗っかった流行である点だ。実は、この妖怪自体に「疫病を治す」伝承があるわけではない。それを祀った神社や塚・碑もない。もちろん、仏様とは無関係。なのに、厚生労働省が「新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ啓発画像」にしてしまったのである(4月9日)。
そもそもは今年2月末、妖怪掛け軸専門店がコロナウイルス対策で「『アマビエ』のイラストをみんなで描こう」と呼びかけ、そのイラストと由来解説をツイッター投稿したのが始まり。これに呼応したツイッター利用者の間で「アマビエチャレンジ」や「アマビエ祭」などのハッシュタグを付けた投稿が一気に増加する。
イラストや漫画は言うに及ばす、中には、ぬいぐるみやフィギュアまで制作するなど、ブームは爆発的に拡がっていく。果ては、日本産のお守りとして海外のネットユーザーまで注目するレベルになっている。
ところが、コロナ禍のスタンスを変えられない大新聞やテレビは、このアマビエブーム報道を“自粛”するばかりで、天下のNHKが報じたのは5月に入ってから。それも地方ニュースの枠である。
「ネットの流行だから、(コスト安で)取り上げやすいんですが、目的や由来がどうであれ、コアな高齢視聴者から『ふざけるな』とクレーム必至の現象なんです。レポーターが直接、取材するわけにもいかないし…」(某テレビマン)
ここで見逃せないのは、次の点だ。
●出現は江戸時代の肥後国(熊本県)。半人半魚の妖怪で、海中から現れ「当年より6年間は、諸国で豊作は続くけれど、疫病も流行する。私の姿を描いた絵を人々に早々に見せよ」と言い残して、再び海中へ。
●ただし、「絵を見せた」ことで、疫病が封じられた記録や伝承はない。疫病退散を結びつけるのは無理筋な妖怪である。
●出現は1846年(弘化3年)の1回きり。ところが、話を聞きつけた瓦版屋がこれを取り上げる。江戸にも情報は伝播したけれど、今年2月末まで最初の妖怪掛け軸専門店が気づくまで、世の中で取り上げられた形跡はゼロ。
JTB総合研究所のレポートには、概ねこうある。
〈過去にたった一度しか公的な記録がなく、極めて『レア』な妖怪・怪異の類であるため、社会的認知度は、極めて低い〉
とした上で、
(1)ツイッター投稿から1カ月の時点で「言い伝えの内容まで知っている」「(話や名前を)聞いたことがある」の合計が約23%。
(2)認知していた人のうち「1カ月以内」に知った人の割合は60%弱。
つまり、わずか1カ月で調査対象の4人に1人が知っていたことになる。新型コロナに“負けない?”感染力、いや拡散力である。
いまや、ブームは全国津々浦々に拡がっている。青森県「アマビエねぷた」、宮城県「アマビエこけし」、愛知県では「アマビエ鬼瓦」を作ってしまった業者もいれば、「アマビエ和菓子」もあちこちで製造・販売され始めている。そして、ついにそれは宗教界へも及んできたのだ。
★神社仏閣もすがるアマビエ
アマビエ護符、お守り、御朱印を配布(領布)する神社や寺が、ブームに遅れるなと続出している。いくつかの神社、寺院にホンネを聞いた。ただし、すべて匿名条件である。
京都のさる歴史的神社の禰宜氏の解説。
「宗教界が、これほどの不況に見舞われるのは、おそらく初めてではないですか。『3密』は痛い。まず、行事ができない。対面での御朱印領布も、高リスクなのでほとんどの神社(京都)は、中止せざるを得なかった。疫病封じで『茅の輪くぐり』が毎年恒例で行われますが、これもやれない。結婚式も延期になるし、さまざまなアーティストとのコラボ企画もダメ。アマビエさんは唯一の救い神なんです」
もちろん、原則は神社や寺院で「手渡し」するのが御朱印や護符と同様だが、原則・建前などにかまっていられない寺社は、ネット通販にも手を出す。
一方、都内の観光寺院に聞くと、
「一番痛いのは、葬儀収入が途絶えたこと。ほとんどのセレモニーホールは休業しているし、会葬などで人が集まるのは御法度ということになっています。檀家からの収入源も減りますし、本堂などの修繕寄附も集まりません」
ちなみに、普通の寺院の収入源は、各宗派とも半分近くが葬儀である。今回のコロナ騒動で深刻なのは、会葬者を集めての葬儀だけでなく、いわゆる個人葬や家族葬までもが自粛を余儀なくされていること。最も痛いのは、
「私たちは公益法人ということになっているし、政教分離の原則もあります。東日本大震災で倒壊・崩壊した寺院や神社が再建しようとしても、一切の公的支援は受けられませんでした。自力再建のためには、檀信徒の浄財に頼るしか手立てはなかった。今回も同じです。建物や墓が壊れたわけではない。でも、それを支える収入基盤が絶たれたも同然です。もちろん、自治体に休業補償を求めるわけにもいかないが、寺で雇っている人は、サラリーマンと変わらない基準で所得税を納めている。住職も法人に雇用されているから、貰った給料から所得税や社会保険料は納めています。その減った分だけでも補ってくれる補償はないものか」
こう発言するのは、法人に約40人の雇用者のいる大寺院の住職である。ちなみに、特定警戒13都道府県には、全国の約4割に相当する約3万4000ほどの寺院がある。
「それ以外の地域にある(自宗の)寺は、いつもと変わらない行事をし、葬儀もやっています。そうした地域が特定地域寺院を支えるやり方を考えないと宗派全体が陥没してしまう」(真宗本願寺派の幹部僧侶)
前編で指摘したように、コロナ騒動は創価学会をはじめ新宗教教団の懐を直撃している。お布施や寄附の減はもちろんだが、
「美術館など併設施設から収入のある世界救世教とか、信者自身の労働奉仕を旗印に、積極的な本部訪問を行動の要にしている天理教などは大変でしょう。PL教団は大花火大会を中止しました。今年、トップの世代交代を考えていた教団はすべて先送りせざるを得ない」(新宗教教団の幹部)
日本には「コレラの慰霊碑」が山形県など、いくつかの地域にある。疫病由来としては、積極的に罹患者の救済にあたった医師や警察官が、逆に「伝染病を撒き散らす者」と住民に撲殺されたことを悼む慰霊碑も多数ある。鳥インフルエンザで駆除された、鶏を弔う碑もある。
こうした伝承はさらに、江戸時代以前の飢饉、疫病慰霊碑にまで連綿と繋がっている。
いずれにしても、「アマビエ」を超える戦略がなければ、宗教界の拡大・発展は起こりそうにない。