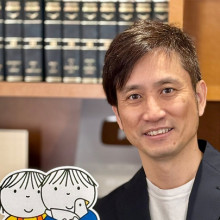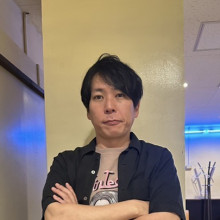3月27日に国内トップの造船メーカー「今治造船」と、2位の「ジャパンマリンユナイテッド(JMU)」が資本業務提携に合意し、新たに合弁会社「日本シップヤード」の設立が決まった。
今回の業務提携は、表向きは業績が低迷するJMUを今治造船が救済するという目的があるようだが、造船業界関係者が本当の目的をこう分析する。
「今や世界の造船市場の2強国、中国と韓国で造船業界の再編が相次いでいる。傍観すれば日本の造船業はボロボロになり、世界市場は中韓に独占されてしまう。グローバル競争で生き残るために日本のトップ企業が手をつないだ、というのが最大の目的でしょう」
韓国では造船業界で世界トップの「現代重工業」が’19年3月に世界3位の「大宇造船海洋」を買収して、持ち株会社「韓国造船海洋」を設立。中国でも同年10月、世界2位の「中国船舶工業集団」と5位の「中国船舶重工集団」が経営統合して、「中国船舶集団」となった。造船の建造量の世界シェアは、単純合算で両社ともに約20%に達する。反面、今治造船とジャパンマリンユナイテッドは、それぞれ5%前後。1社では、とても太刀打ちできなかったのだ。
そもそも、中韓の大手造船会社が経営統合を進めているのには、大きな理由がある。1つは「一括発注の増加」だ。
「最近は海運業界で再編が進み、それにつれて大型商船も10隻まとめての一括発注がしばしば起きています。小さな会社では到底それらの要求に応えられないため、造船会社で再編が進んだのです」(同)
特に韓国は利幅が高いLNG(液化天然ガス)運搬船の受注に力を入れているという。
「現在、LNG運搬船は一隻200億円という高価格でカタールなどから大量発注が続出している。英国海運分析機関の調べでは、’19年当初で韓国は、136隻発注中、100隻も受注しているという。それに対して、日本は’16年から受注ゼロです」(経営アナリスト)
さらに、世界の海運業界で起きているのが深刻な“船余り”だ。
「’08年に起きたリーマンショック直前には、船舶が大量発注された。その反動で、船舶が余って需要が激減。そのため、各国造船企業の間で壮絶な“新規受注争奪戦”が始まり、その競争を戦い抜くために中韓の造船企業は経営統合を進めたのです」(国内造船メーカー勤務の男性)
ただ、韓国の現代重工業が大宇造船海洋を買収したのには裏事情があるという。
「大宇造船海洋は一時経営危機に陥っていたのですが、世界の造船市場の独占を目論んでいた韓国政府が、裏で1兆2000億円の金融支援をしてバックアップ。政府の公的支援が安価な受注につながり、市場価格をゆがめることになりました。日本政府は2018年秋に、韓国の支援措置がWTOの協定違反に当たると主張。公正な競争環境がゆがめられているとして支援措置の見直しを求めましたが、韓国は大宇造船海洋を現代重工業に買収させることで消滅させて、その批判を封じ込めたのです」(同)
韓国が暴挙に出るほど造船業を支援するのは、20代の失業率が10%にも達する同国の経済不況が原因にある。造船業界を活性化させ、そこに雇用を生み出したいという強い思惑が働いているのだ。
一方、日本の造船企業は国のバックアップもなく、国内企業同士の連携もなかった。
「最近になり、ようやく日本の造船企業も内輪でバトルしている暇はない、ということに気づき始めた。それが今回の提携です。暴走する中韓を打ち破るには日本の高い技術力を活かし、いかに価格競争に打ち勝つかです」(同)
ただ、1901年に創業した今治造船は、創業家の桧垣一族の強いリーダーシップのもとに経営してきた“同族企業”で、JMUは「日本鋼管」、「日立造船」、「石川島播磨重工業」、「住友重機械工業」といった総合重工メーカーを源流とする“重工系企業”。今回、育ちが異なる「水と油」の企業が業務提携したことになる。
「一種の賭けではありますね。地場系の今治と、技術に秀でたJMUが提携することは、日本の造船業界に新たな流れを作るのでは、という期待も膨らんでいますよ」(前出・経営アナリスト)
今回の業務提携が、世界をリードしてきた日本の造船企業復活の狼煙となるのか。